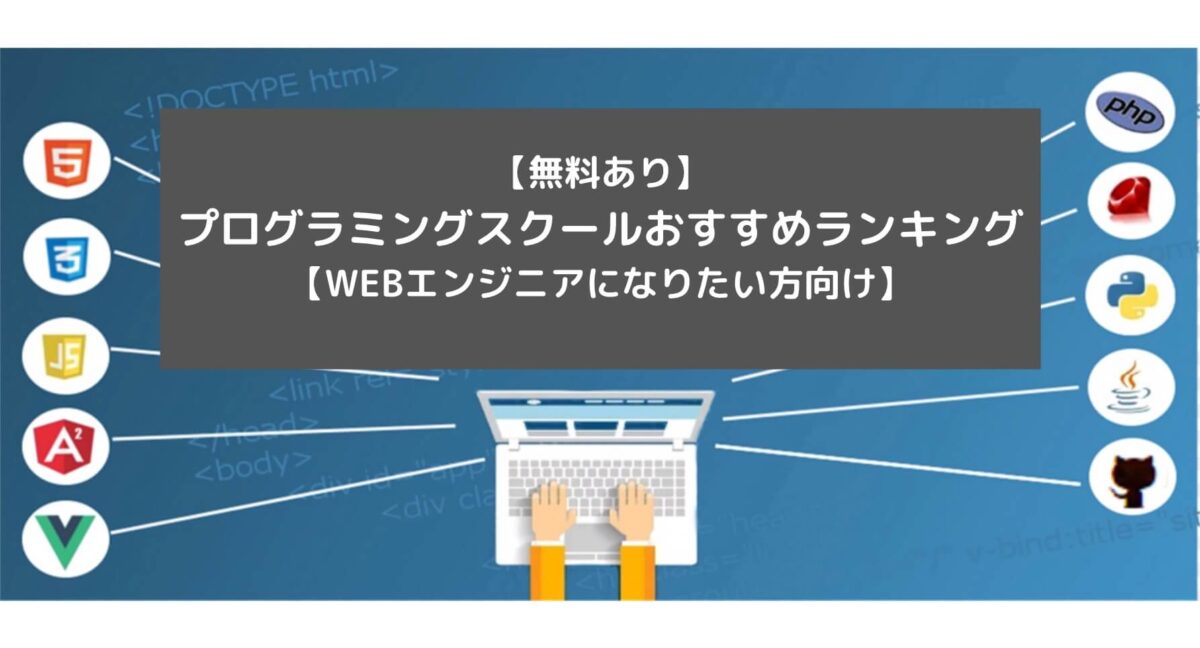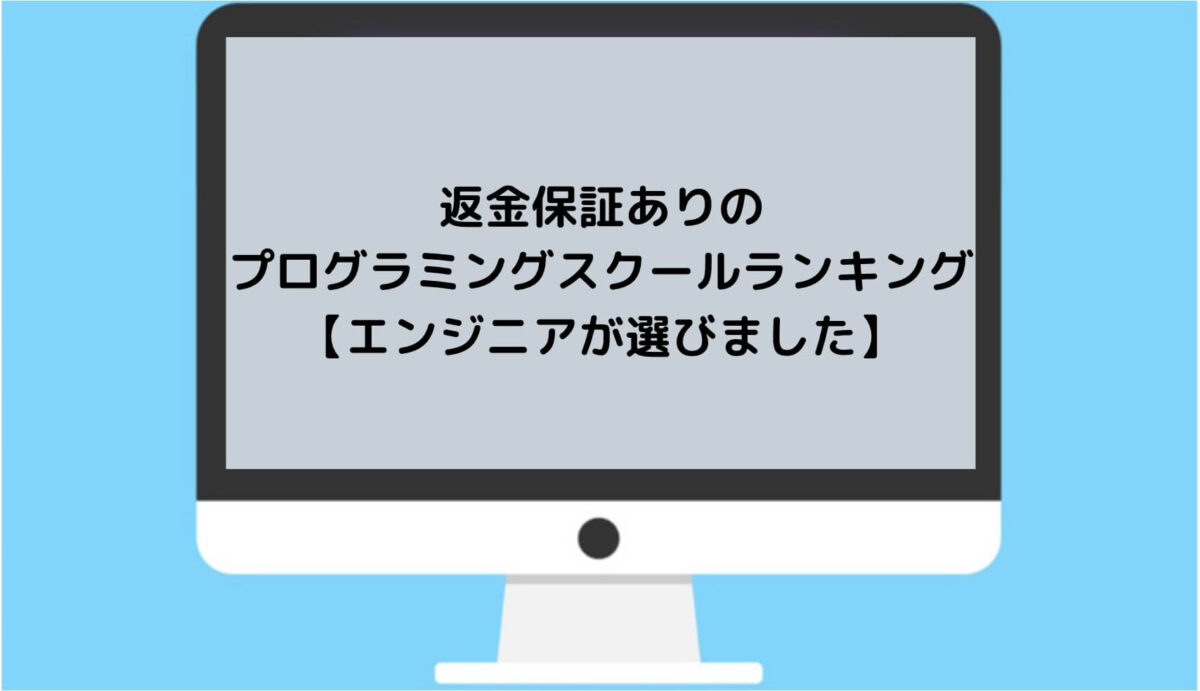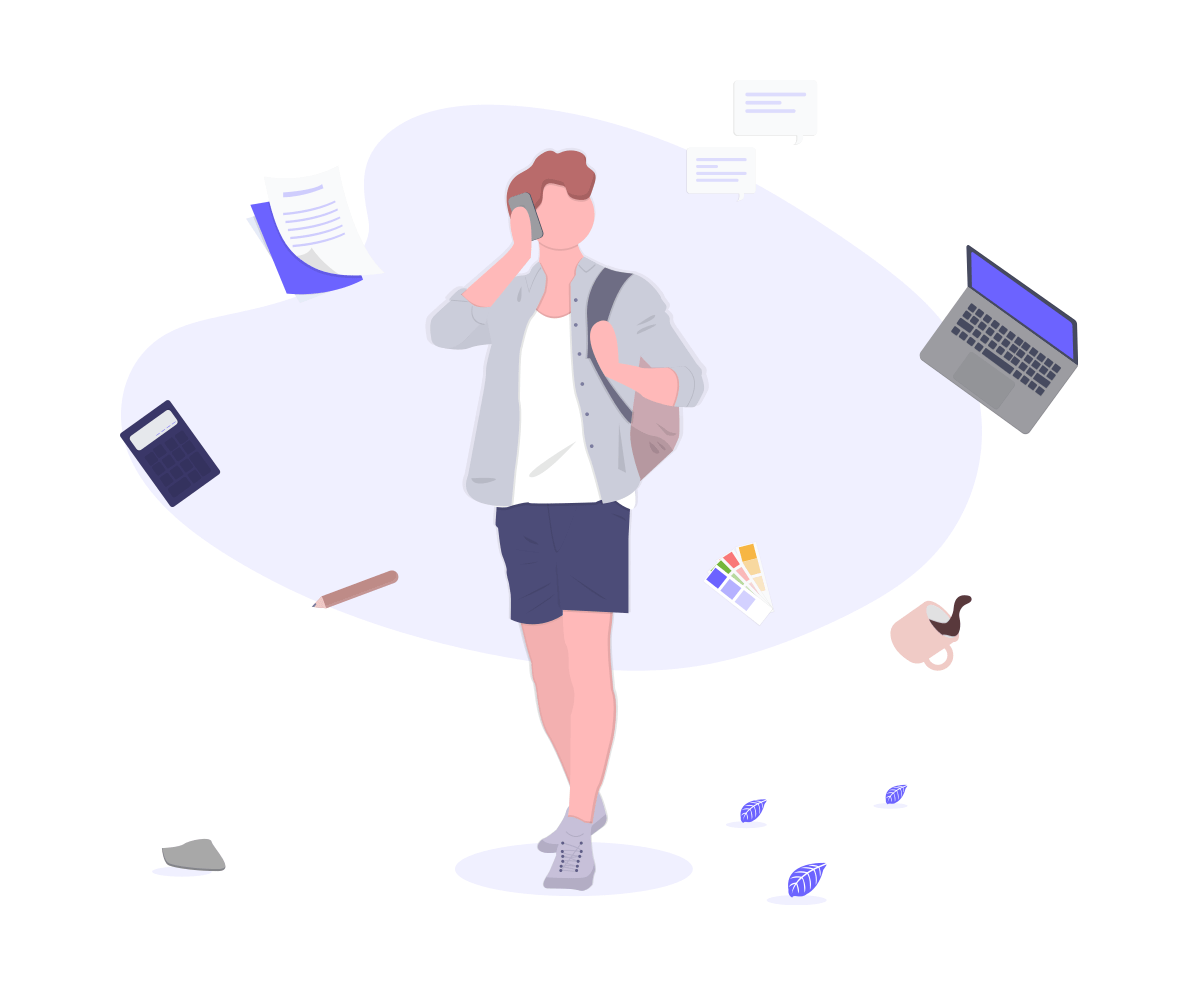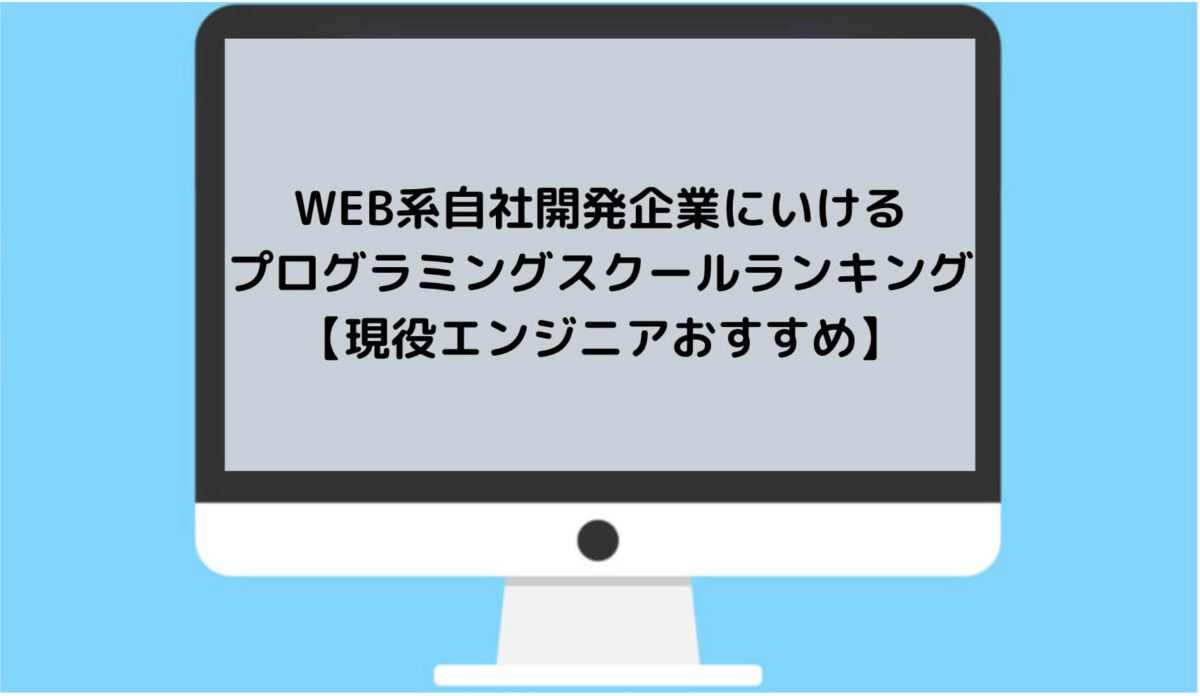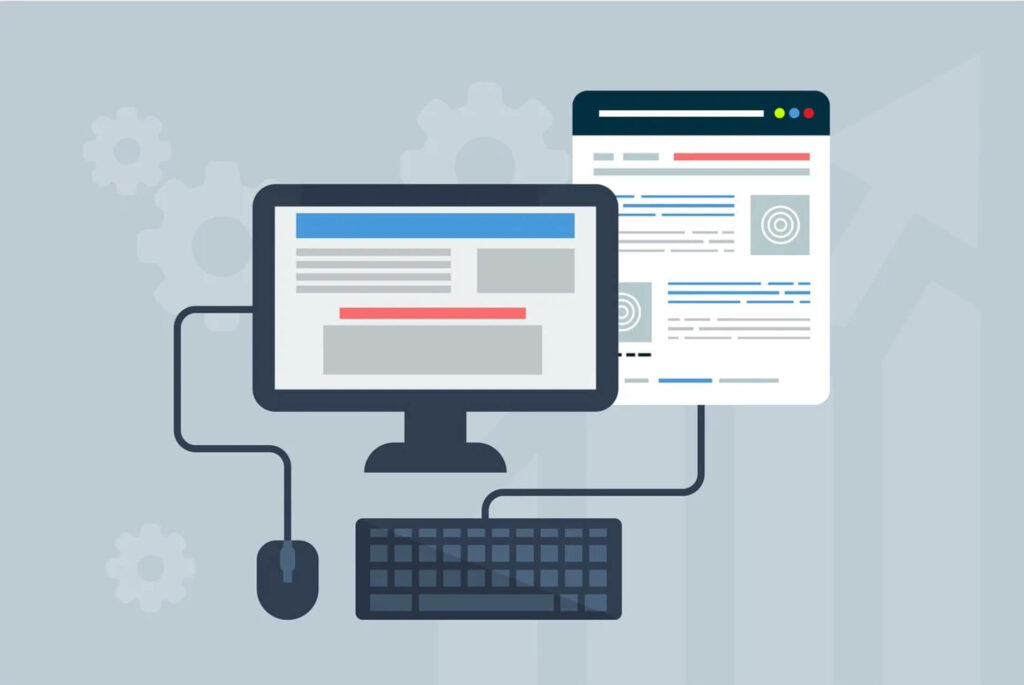
最近のエンジニアブームはすごいですね。
「未経験だけど新卒でエンジニアになりたい」という方も増えている気がします。
つい、先日も昔の知り合いから「大学出たらエンジニアになりたいんだけど、何やったらいい?」と聞かれてビックリしました。
それぐらいエンジニアという仕事の認知度は高いんだなぁと。
ちなみに僕は未経験からプログラミング学習を開始。
大学中退後エンジニアとして就職しました。
周りが新卒の段階ではフリーランスエンジニアとして独立しており、年収は1000万円ほどでした。
そこで、今回は新卒でWEBエンジニアを目指す方に向けて、「何をするべきか」という話について深堀りしていきます。
新卒で就活したことはないですが、未経験からエンジニアになったのには変わりません。
それに、わりと早い段階で稼げるようになっているので、参考になるかなと思います。
未経験から新卒でWEBエンジニアになるために必要なことを教えます
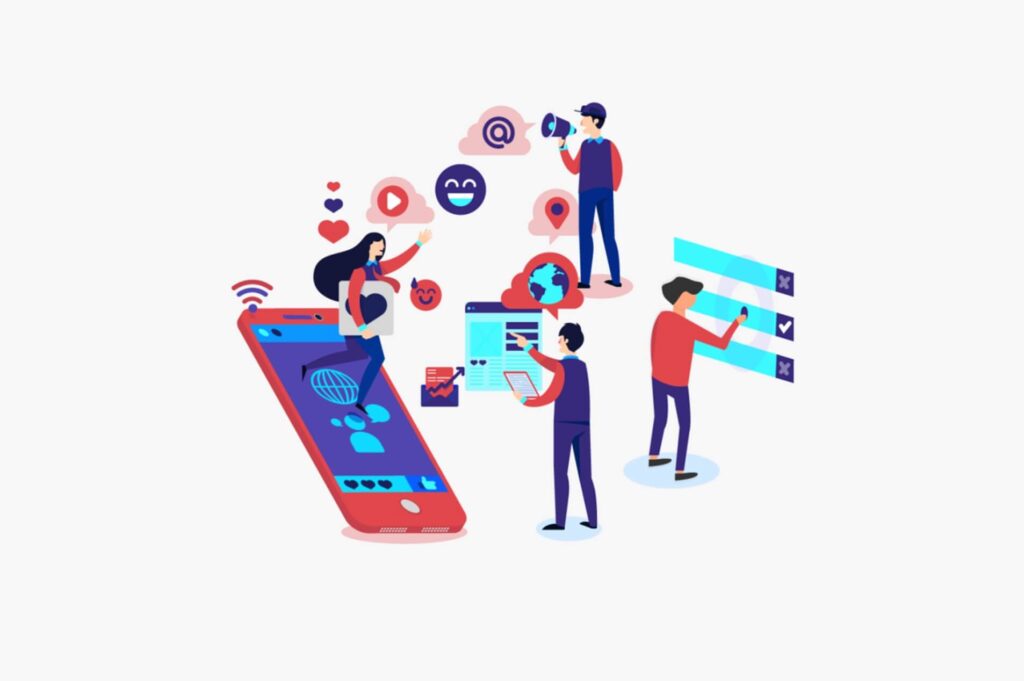
結論から話すと「基本を身に着けつつポートフォリオを作って就活しよう」です。
ポートフォリオというのは、あなたがプログラミングを使って作ったオリジナルサービスのことです。
で、このポートフォリオがあると就活では結構有利になります。
それに、作る段階でかなり力もつく。
間違いなく作るべきです。
僕自身もポートフォリオがあったおかげでかなりスムーズに就活を進めることができましたよ。
・基本学習
・ポートフォリオ制作
この2つをクリアする方法について紹介しますね。
①基本学習
基本学習ですが、大前提として「独学」「プログラミングスクール」の2択になります。
個人的にはスクールがオススメです。
僕自身もスクールに通いました。
両者のメリット・デメリットは次のような感じです。
| メリット | デメリット | |
| 独学 | ・費用がかかりにくい | ・挫折しやすい ・難易度高め |
| スクール | ・確実にスキルを習得できる ・ポートフォリオまでセットで制作できる | ・費用が多少かかる |
独学する場合は次の学習サービスが使えます。
スクールの場合は、【無料あり】プログラミングスクールおすすめランキング【WEBエンジニアになりたい方向け】を参考にしてみてください。
(スクールでは基本学習からポートフォリオ作成までできます)
-
【無料あり】プログラミングスクールおすすめランキング【WEBエンジニアになりたい方向け】
あなたプログラミングスクールに通いたいけどたくさんありすぎてどこがいいのかわかりません。 最近はエンジニアブームということもありプログラミングスクールが増えました。 一方でたくさんありすぎてど ...
続きを見る
僕が実際に受講した上でランキング化していますので、わりと参考になるかと。
②ポートフォリオ制作
基本学習が終わったら、次はポートフォリオの制作をやるべきです。
冒頭でも話しましたが、ポートフォリオがあるとかなり就活で有利になります。
それに、WEBエンジニアとしてのスキルも高まりやすいです。
個人的には、ポートフォリオ制作は誰かに教えてもらったほうがいいと思います。
理由は、単純に「独学だと難しい」からです。
・身近にいるプログラミングができる友人に教えてもらう
・MENTAなどのサービスを使ってメンターを見つける
・スクールで講師に教えてもらう
上記のような選択をすると良いと思います。
ちなみに僕はプログラミングスクールに通いました。
疑問点をすぐに解消できるし、ポートフォリオも完成させることができるし、かなりよかったです。
就活段階で意識すると良いことを紹介します
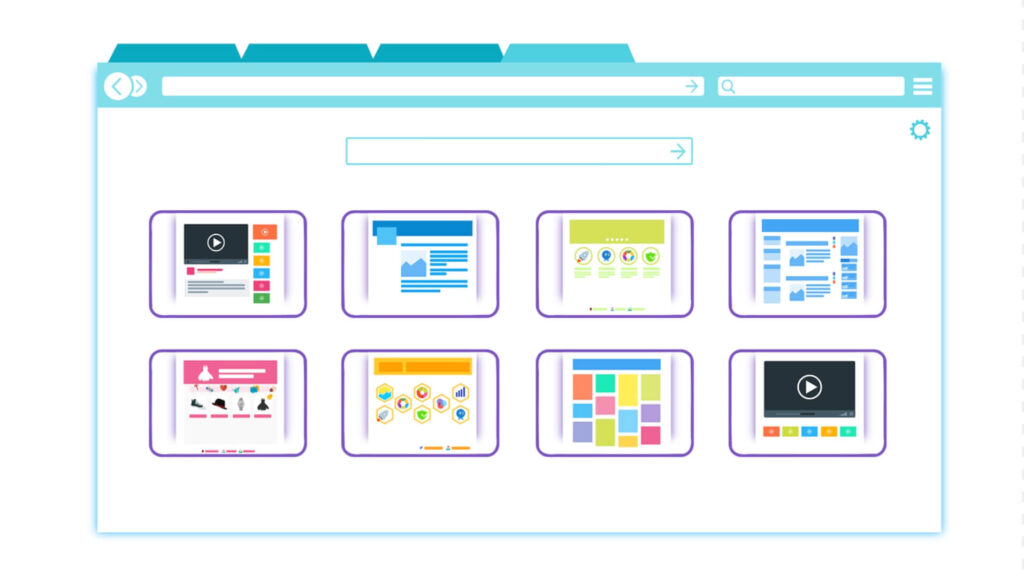
ポートフォリオまで作成できたら、あとは就活をしてエンジニアになるだけです。
ぶっちゃけ、新卒でWEBエンジニアを目指すのってそれほど難しくはないです。
基礎学習・ポートフォリオ作成をクリアできているのなら、まず1社は内定をもらえると思います。
しかし、大事なのは企業選びです。
ハズレの企業を選ぶと、なかなかスキルが身につかなかったり成長できなかったりします。
そこで、優良企業の選び方や、優良企業に入るために有効なアピール方法などを紹介します。
参考にして、就活を攻略してください。
超大事:スキルが身につく会社に行けないと先が辛い
まず、絶対に覚えておいてほしいのが「スキルが身につく会社に入れないと、その先が辛い」ということです。
WEBエンジニア業界はあなたの想像の何倍も実力社会です。
実力がつかないと、年収も上がらないです。
実際、30歳、40歳になってもスキルがないために年収300万円ぐらいの方だっています。
逆に、20代で年収1000万ほどになっている方もいます。
自慢ではないですが、僕もその1人です。
だからこそ、今後のキャリアを考えても、なるべく実力が身につく会社に就職するべきなのです。
ここは絶対心に留めておいてくださいね。
 スキルが身につく会社の特徴
スキルが身につく会社の特徴
「じゃあ、どういう会社に入ればいいの?」と思う方もいるかと。
結論から話すと次のような会社です。
・LINE
・メルカリ
・楽天
・サイバーエージェント
しかし、上記のような会社にWEBエンジニアとして入ることができるのはほんの一部の人間です。
だから、本質的な部分を見て、行くべき会社を判断しましょう。
具体的には、次のような特徴をもっている会社にWEBエンジニアとして就職するべきだと僕は思います。
・企画ができたり、意見を通したりできる
・実装できる(開発経験を積むことができる)
・それなりに需要のあるツールや技術が使われている
・開発スタイルがしっかり確立されている(スクラムだったりアジャイルだったり)
・先輩エンジニアが優秀
こういう会社に入ることができれば、あなたもしっかりスキルを身に付けることができます。
「1人前のエンジニア」にもなることができる可能性も高いです。
 ググって探せばOK
ググって探せばOK
で、成長できる会社の探し方ですが、まずはメガベンチャー(LINE)などを狙い、実力的に無理そうなら、後はググって探せばOKです。
ググった時に、出てきた会社の応募要項に次のようなことがしっかり書かれていいるかチェックしておいてください。
・使用技術
・作成しているサービス
・エンジニアの先輩の様子
上記のようなことがハッキリ書かれていなくて「未経験OK!!」とか書いてある会社は避けてください。
そういう会社って、いきなり携帯販売とかさせたりしてきます。
つまり、開発と全く違うことをやらされるわけです。
入ると、エンジニアとしてはもちろん、人間としてもまったく成長できない可能性もあるので注意です。
アピール方法
企業への応募時のアピール方法ですが、次のような点を意識すると良いかと思います。
・学習熱心であること
・なぜ応募先の会社を選んだのか
・貢献したいこと
上記のことをしっかりアピールすれば大丈夫だと思いますよ。
特に「なぜその会社なのか」ってところをハッキリ言えるといいですね。
作っているサービスが好きとか言うと、企業は喜んでくれること多いですよ。
あと、くれぐれも次のようなことは言わないでくださいね。
・学習させて欲しい
・将来的にフリーランスエンジニアになりたい
心の中で思っていても絶対に口にしないでください。
企業からすると、こんなことを口にするあなたを雇うメリットってないですので。
「学習させて欲しい」とか、企業からすると「うちを勉強するところだと思っているのか?」という反感しか抱きません。
あと「将来的にフリーランスエンジニアになりたい」とか「どうせ辞めるやつ雇うわけ無いだろw」って感じになります。
なんか、この辺がわからないで、素直に面接や履歴書で伝えてしまう新卒の方がいるそうですが....。
やめてくださいね。
未経験から新卒でWEBエンジニアになるのはかなりオススメ

ということで、今回は未経験から新卒でWEBエンジニアになる方法や、就活の際の重要ポイントについて解説しました。
あとは、この記事に書いてあることを参考に行動すればOKですよ。
最後に、僕自身の意見ですが、未経験から新卒でWEBエンジニアを目指すのはかなりオススメです。
とくに、「他にやりたいことがない」のなら一旦目指しておいても良いと思います。
オススメする理由は次のようなところですかね。
・手に職
・リモートワークできる
・年収も良い
・将来性あり
転職とかしやすかったりしますし、かなり快適に働くことができる業種だと思います。
2年目から年収を2~3倍にすることも十分可能
あと、給料の面ですが2年目から年収を2~3倍にすることも可能です。
これ、めっちゃ魅力的。
僕自身も、1年目は月給20万円ちょっとだったのですが、2年目からはフリーランスエンジニアになって月給60万円ほどになりました。
2年目で年収720万円ほどって結構良くないですかね?
フリーランスエンジニアになれば、若さとか関係なく、実務経験歴と実力で稼ぐことができますよ。
ちなみにフリーランスエンジニアになる方法はフリーランスエンジニアになるには何をすればいい?【方法と全行程を詳しく解説します】にまとめています。
気になる方はぜひ。
 わりと自由に楽に稼げます
わりと自由に楽に稼げます
フリーランスエンジニアになると、結構自由&楽に稼げますよ。
僕は、次のような生活を送っています。
・朝はゆっくりおきる
・休みたい日は休む
・良いマンションに住む
・貯金もできるのでメンタルも安定
・好きな場所で仕事
もし、あなたが「あーそういう生活したいわ」と思うのであればWEBエンジニアという選択肢はかなりアリかなと。
少なくとも僕は、WEBエンジニアになって後悔したことないです。
むしろ、周りの人の仕事の話とか聞いていると「自分恵まれているな」と感じます。
てことで、今回は以上です。
応援しています。